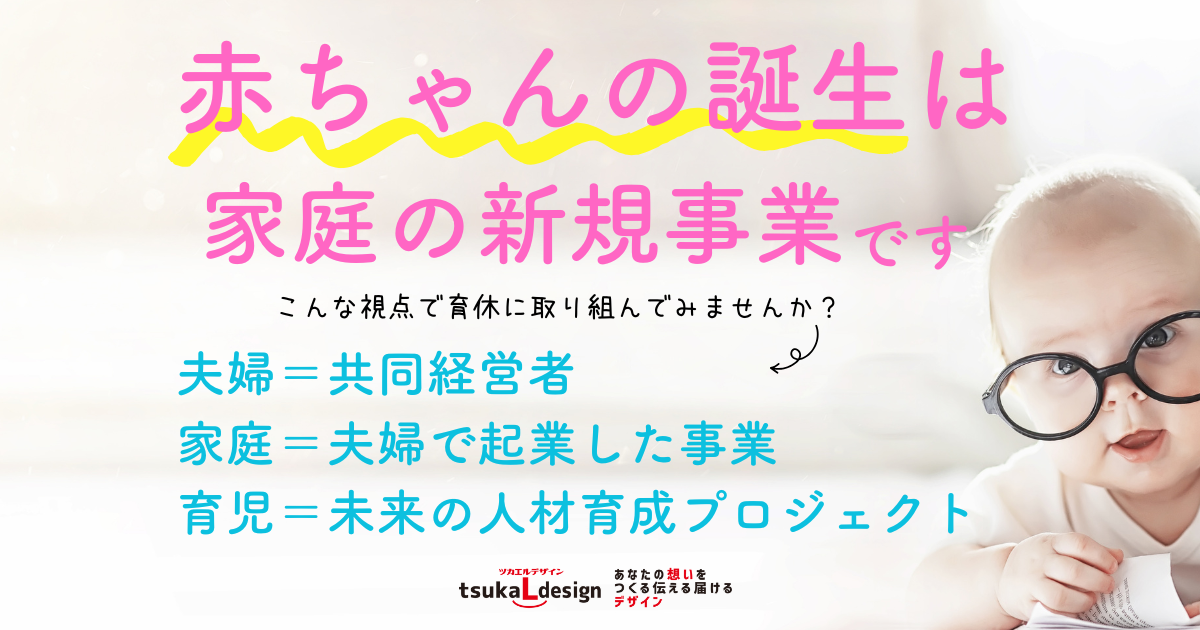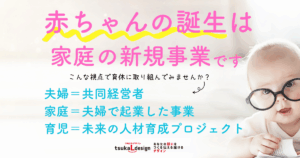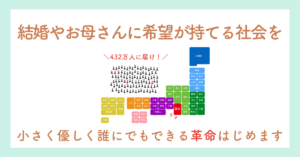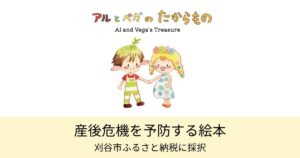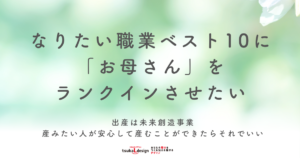2024年7月から産後支援ブログにリニューアル
産後の夫婦にとって役立つ記事と、男性育休支援のことを載せていきたいと思います。
自己紹介などはこちらをご覧ください → tsuka L design
出産=スタートアップ——育休を“仕組みづくりの期間”に変える発想
「なるほど!この視点は無かった!」男性や経営者の方に響いています

こんな風に考えてみてください。
家庭で育成された人材は、約20年後あなたの会社にも「新卒」としてやってきます。
どんな人材が来て欲しいですか?優秀で企業の戦力になってくれる人が来て欲しいですよね?
しかし、少子化などで採用は困難になっていると聞きます。
20年後の日本経済を考えると、人材を創出し育成してくれる「家庭」を支えることは未来に直結する投資です。
100年後、今いる人間は総入れ替え。だからこそ、家庭と企業はもっと協力しないといけない。
今までと違う視点で「育休」について考えてみませんか?
序章:視点を変えたら、届く相手が変わった話
家事育児は男性がやるものじゃない──
そんな思い込みがまだまだ残っています。
でも、家庭の話を“ビジネス視点”で語るようにしたら、男性社員・管理職・経営者にまで一気に届くようになりました。
「家庭って、ビジネスと同じなんだ」
そう感じてもらえた瞬間、世界は大きく変わります。
ここからは、私が普段お話ししている 家庭と企業をチームにする話 を、お伝えしていきます。
ぜひ最後までお付き合い頂けると嬉しいです
1:家庭を組織に置き換えると見えてくる“構造の問題”
家庭を“ひとつの組織”と見立ててみると、驚くほど多くの問題が構造として浮かび上がります。
まず、家庭には“担当者”という概念がありません。
企業であれば、誰がどの役割を担い、どの仕事に責任を持つかが明確です。
しかし家庭では、「なんとなく妻がやる」「なんとなく夫がやる」といった曖昧な状態で運営されています。
本来必要な
- 業務分担
- 業務量の見える化
- 情報共有
- フォロー体制
これらが整っていないため、トラブルが起きるたびに混乱し、責任の押し付け合いが起きてしまうのです。
産後に負担が一気に偏るのも、
「誰が何をやるかが曖昧なまま新規業務が爆増する」
という構造的な問題が原因。
誰かが悪いのではなく、仕組みが存在していないだけ。
そう考えると肩の力がすっと抜けます。
2:結婚=起業、出産=新規事業、育休=スタートアップ期
家庭というチームは、企業と同じように成長フェーズがあります。
結婚
…パートナーと“組織を立ち上げる”起業フェーズ。価値観や文化の擦り合わせが必要です。
結婚して夫婦になる=独身(個人事業主)から、共同経営者を迎えて法人化(事業拡大)するイメージです
家庭の運営=家庭内にも色々な業務があります。協力して運営する事は、経営の健全化(夫婦円満)に必須です
出産
…子どもという“新規事業”がスタートする瞬間。喜びと同時に、抱える業務量は一気に跳ね上がります。
赤ちゃんの誕生=新規事業のスタートです。20年はかかる、長期プロジェクト。次世代の人材を育成します
二人目、三人目の子どもが生まれるのは、新規事業を複数抱える事と同じです。
育休
…本来はスタートアップ期。新しい事業の基盤を整える、最も重要なフェーズです。
家庭と育児の運営=以前と業態が変化し、頼みの綱である妻は出産によるダメージで戦力外になります。
共働きの場合、育休後の家庭は担当者不在の部署となるため、育休中に業務改革や仕組みを整える必要があります。
ところが、企業なら必須の
- オンボーディング(初期設定)
- 業務設計
- 情報共有
- リスク管理
- 引き継ぎ
これらが家庭ではまったく設計されないまま走り始めてしまう。
その結果、産後の混乱は「必然」として起きてしまうのです。
3:イレギュラーは必ず発生する──だから仕組み化が必要
子どもが生まれた家庭では、イレギュラー(想定外)が日常的に発生します。
- 突然の発熱
- 呼び出し
- 睡眠トラブル
- 送迎の急な変更
- 家事の滞留
- ママの体調不良
- 夜泣きで寝不足
企業なら、イレギュラーは“想定内”として扱います。危機管理もバックアップ体制も整えます。
なのに家庭では、「なんで今日に限って?」「急に言われても困る」と、毎回ゼロから混乱が起きる。
実は、仕組みさえ整えてしまえば、家庭のイレギュラーの8割は事前に潰せる
ということを、もっと多くの人に知ってほしい。
家庭の仕組みがあるだけで、夫婦の衝突は減ります。
パパが活躍できるシーンはきっとこの部分なのではと思うのです。
4:共育・共育ちという新しい概念
今は“育児”ではなく、“共育(ともいく)”という言葉を使うんだそうです。
育児は「子どもを育てる」だけど、共育は「夫婦が共に育つ」。
この期間は、誰かが一方的に頑張るフェーズではありません。
- 夫婦で学ぶ
- 夫婦で成長する
- 夫婦で未来をつくる
これこそが“共育ち”です。
そして共育ちした家庭で育つ社員は、企業でも伸びやすい。
なぜなら
- 課題解決力
- コミュニケーション力
- 予測力
- 感情コントロール
- 優先順位の判断
これらが育児と深く結びついているから。
共育は、企業の人的資本にもつながっていきます。
5:育休の取り組みを“資産”に変える方法
育休中の取り組みは、社員の「個人の努力」で終わらせてしまうにはもったいない。
それは、企業にとっても大きな価値を持つ“資産”になります。
- 育休中どんな仕組みを作ったのか
- 家庭のどんな課題をどう解決したのか
- パートナーとどんな対話を重ねたのか
- イレギュラーにどう対応したか
- どんな成長があったか
これらをレポートとして可視化することで、採用広報にも使え、評価制度にもつなげられます。
さらに、テレワークで社内の交流が減る中で、
家庭で生まれた学びは部署を超えたコミュニケーションの“交流の種”にもなります。
企業と家庭が“共育”の視点でつながる未来が、ここにあります。
6:家庭と企業をチームにする──橋渡しの具体策
では実際に、どんな取り組みが家庭をチーム化するのでしょうか。
具体的には、こんなステップがあります。
- 家庭の業務をすべて洗い出す(見える化)
- 得意・不得意の棚卸し
- 役割分担を固定ではなく“柔軟なチーム制”にする
- イレギュラー発生時の対応ルールを事前に決める
- 二人で情報共有の仕組みを作る(Googleカレンダーなど)
- 育休中に“家庭のオンボーディング”を整える
ポイントは、「どっちがやるか」ではなく、家庭という“チーム”をどう運営するかに視点を置くこと。
これだけで産後の負担は大きく変わります。
7:家庭が整うと、企業も整う──双方が得する未来
家庭が整うと、社員の心理的安定が上がります。
心理的安定が上がると、パフォーマンスも上がります。
- 離職率の低下
- エンゲージメントの向上
- “家庭力”を持つ社員は採用でも好印象
- 組織全体が穏やかで協働的になる
家庭力のある社員は、企業にとって間違いなく“強い”。
家庭と企業は、対立するものではありません。
本来は、互いの力を高め合う関係です。
家庭はもっとチームになれる。だから私はこの活動を続けている
私は、産後の混乱が「個人の能力不足」だと思われる社会に違和感があります。
本当は、構造の問題。仕組みがなかっただけ。
家庭にもチーム運営が必要で、ビジネス視点を入れると誰にでも理解してもらえます。
家庭が整い、企業が整い、社会が整う。
その橋渡しこそが、私の役割だと感じています。
何から始めればいいか考えた時、ハードルになるものがあります。
それは、意識を合わせること。育った環境が違ったり、「アタリマエ」と思う事は意外と違うものです。
絵本を使ったスゴロクワーク体験会などで、産後や育休について触れる機会から始めるのがおすすめです。
体験会やセミナーなど開催しておりますので、お気軽にお問い合わせください。